弁理士試験の最初の関門、短答式試験は例年5月中旬から下旬に行われます。したがって、ゴールデンウィークに差し掛かるといよいよ試験本番が間近に迫ってきたことを実感するかと思います。
この記事では、私の弁理士試験の合格体験を基に短答直前期の勉強法と過ごし方について解説します。
弁理士試験の勉強法全般については、下記の記事で解説しています。
弁理士試験独学のためのおすすめ参考書と勉強法
短答試験の合格点と難しさ
短答試験は60問60点満点で試験時間は3時間30分です。60問の内訳は下記の通りです。
合格基準点は例年39点で、特許法・実用新案法は8点未満、その他科目は4点未満の科目が一つでもあると合計点に関わらず不合格(足切り)となります。
- 特許法・実用新案法:20問
- 意匠法:10問
- 商標法:10問
- 条約:10問
- 著作権法・不正競争防止法:10問
上記はあくまで過去の実績データを基にしているので最新の試験情報は特許庁のホームページで確認しておきましょう。
短答試験では30点を超えるまでは勉強量と得点の伸びがおおよそ比例するのですが30点を超えると勉強量に対して得点が伸び悩む「停滞期」が訪れ30点台半ばを行ったり来たりします。
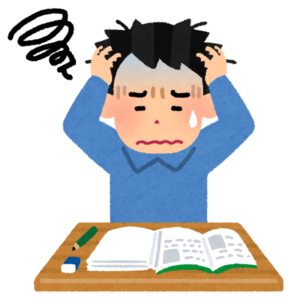
そして、その停滞期を抜け出して他の受験生よりも一歩前に進むことができた受験生だけが合格することができます。
短答試験の合格率は私が受験したときで約11%でしたので他の受験生より一歩前に出て10人の中の1人になることがかなり難しいことがわかると思います。
ちなみに、恥ずかしながら私は39点ギリギリでの合格でした。得点の内訳は下記の通りです。
- 特許法・実用新案法:11点/20点満点
- 意匠法:8点/10点満点
- 商標法:6点/10点満点
- 条約:7点/10点満点
- 著作権法・不正競争防止法:7点/10点満点
したがって、たかが1点で泣く人が大勢いますし、私のように首の皮1枚でつながった人もいます。
短答直前期はその1点を全力で取りにいくつもりで最後まで勉強し尽くしましょう。
模試で本番同様の環境に慣れておく
どの試験でも直前期は本番同様の環境と試験に慣れておくことはとても重要です。
直前期になると各資格予備校でも模試が開催されるのでできるだけ受けておきましょう。私もLECやTACの模試をできるだけ受けておきました。

模試で時間管理をしっかりシミュレーションしておき、独特の環境でも実力を出し切れるようにします。また、模試の結果は冷静に振り返り、同じようなミスをしないようにします。
一方で模試は本番より難しめに作られていると思うので、例え模試で合格点に届かなくても落ち込まないようにします(無論間違えた問題の反省は必要です)。
逆に合格点を超えていれば自信をもって本番に臨んでください。ちなみに、私は34点と一度も合格点を超えられませんでしたが本番でギリギリ合格できましたので模試の結果で落ち込んだり諦めムードになるのは早計です。
短答直前期の勉強法
試験直前期なので、中途半端に新しい知識をインプットするよりも今ある知識をしっかりと本番でアウトプットできるように勉強することが大事だと思います。
資格予備校にしてもオンライン講座にしても模試、講座のテキスト、条文、過去問を中心に勉強します。
過去問の潰し込み
過去問については、10年分について、わからなかったり間違える問題がなくなるまで潰し込むように勉強します。短答直前期までには潰し込みを終わらせておきたいところです。
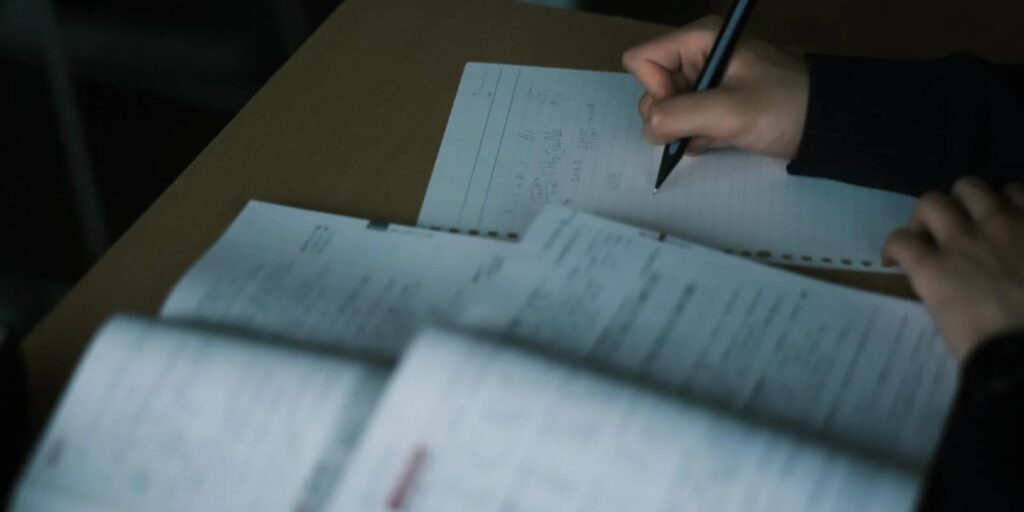
条文(四法対照)の読み込み
弁理士試験は条文の試験であるため、条文の読み込みも行います。とはいえ、漠然と眺めても定着しないので下記のようにメリハリをつけて1点を貪欲に取りに行くつもりで読み込みます。
- 模試や過去問を解いて苦手なところに力を入れる
- 特許、実用新案、意匠、商標の違いを意識しながら読み込む
- 下記のように科目ごとに重みづけをしながら読み込む
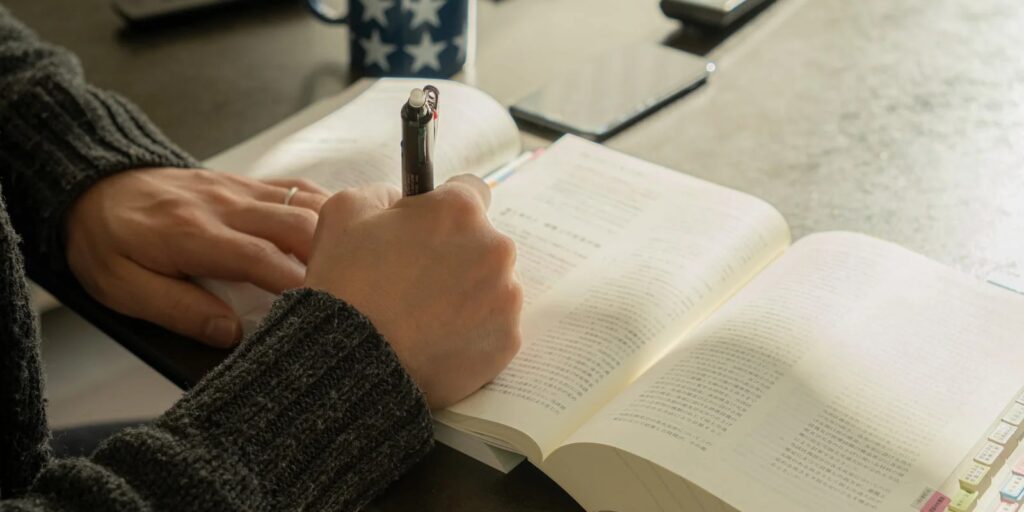
特許法・実用新案法は特に重要
特許法・実用新案法は20問とボリュームも大きいですし、意匠法、商標法とも関連するので特許法・実用新案法で得点が取れないとかなり厳しいです。私も特許法・実用新案法でもう少し点が取れていればギリギリではなく余裕を持って合格できたと反省します。
したがって、特許法・実用新案法は最優先で勉強するようにしましょう。
逆に特許法・実用新案法の知識がしっかり固まっていれば、特実との違いを意識できるようになり、意匠、商標も得点が伸びてきます。
下三法はメリハリをつけて勉強
下三法(条約、著作権法、不正競争防止法)は、深入りすればいくらでも勉強することができますが、時間をかけ過ぎて上四法(特許、実用新案、意匠、商標)が疎かになっては合格は遠のきます。
したがって、全て完璧を目指すのではなくある程度の割り切りが必要です。私の経験に基づく割り切りのポイントは下記の通りです。
- 条約は、条文数が多く特にPCT規則まで含めると覚えることが莫大になるので、深入りしすぎずに基本的問題(過去問や講座のテキストレベル)を確実に解けるようにして足切りを回避
- 著作権法は、ある程度勉強を進めると点が伸びにくくなるので、深入りしすぎずに基本的問題(過去問や講座のテキストレベル)を確実に解けるようにして足切りを回避
- 不正競争防止法は、勉強量に対して得点が伸びやすいので全問正解を狙う
試験前日の過ごし方
会場までのルートを確認
当たり前ですが、時間通りに会場に到着できなければ試験は受けられませんし、道中で焦って余計なことに頭を使うと実力を出し切ることもできません。
利用する交通機関やルートをしっかりと確認しておきましょう。前日に会場の下見までできればベストです。

持ち物の確認
受験案内で必須の持ち物として書いてあるものは絶対に忘れずに持ってくるとして、その他に必要なものをまとめました。
飲み物と昼食
試験は午後からスタートで昼時は移動でバタバタしたり混雑したりとのんびり昼食できないこともあるので昼食は持参して会場でさっと食べるのがよいと思います。食べ過ぎて試験中にお腹を壊しては困るので胃腸に優しいものを最低限食べておきます。私は、試験のときカロリーメイトとバナナをサッと食べるようにしています。
また、試験中に水分補給が必要なので、受験案内をよく読んで禁止されていない飲み物を持参しておきましょう。
重ね着で体温調節
試験会場の温度は寒かったり暑かったりしてコントロールできないので、脱いだり着たりして体温をコントロールできるような服装で来るようにします。それでも、寒かったり暑かったりするときは、温度で1年を棒に振るよりも遠慮せずに試験官に相談しましょう(運が悪いと冷房の吹き出し口直近の席に当たることもあるので)。
使い慣れた教材
試験会場ではリラックスして平常心を保つことが重要ですので試験会場で直前まで必死に勉強するのはおすすめしませんが、使い慣れた教材を持ってきて確認することで平常心を保てるのであれば、お守りとして持ってくることをおすすめします。
体調管理と睡眠
夜遅くまで勉強したい気持ちはわかりますが、体調を崩したり睡眠不足で実力を出し切れなくては本末転倒ですので、腹八分目くらいに抑えて早めに寝ましょう。
勉強するなら頭が冴えている当日午前の方がよいです。
試験本番での注意事項
前日にしっかりと持ち物や会場までのルート確認して十分な睡眠をとったらいよいよ試験本番です。私が特に気を付けたことを以下にまとめます。

会場には早めに到着しておく
試験当日は公共交通機関の遅延やその他トラブルで予定通りに移動が進まないことが起こり得ます。したがって、先ずは「必要な持ち物をしっかりと持って時間通りに会場に到着する」ことを最優先で行動します。お昼も持参して会場で食べるようにしました。
こうすることで、試験そのもの以外のことに極力頭を使わないようにして、平常心を保つことができます。
自分の机を入念に確認
自分の机に到着したら、机の上の落書きや机の下に何か入っていないかしっかり確認します。他人のものであったとしても試験中に試験官に指摘されたら不正行為として一発で終わりです。
休憩時間は一人になる
休憩時間は外に出てリフレッシュするとよいです。他人の出来不出来を聞いても心が乱れるだけですし、一人になって平常心を取り戻し気持ちを切り替えるようにするとよいです。
トイレと水分の摂りすぎに注意
試験中にトイレに行きたくならないように休憩時間中にトイレは済ませておきます。また、水分の摂りすぎにも注意しましょう。それでも、トイレを我慢できない(トイレで試験に集中できない)ときは試験官に伝えて指示を仰ぎましょう。
まとめ
以上、短答試験直前期の勉強法と過ごし方についてまとめました。試験前日までは1点を必死で取りにいくつもりで徹底的に勉強し、試験前日、本番は、勉強というよりも試験を確実に受けて実力を出し切るための準備に集中した方がよいと思います。
受験生皆様の健闘をお祈りしています。

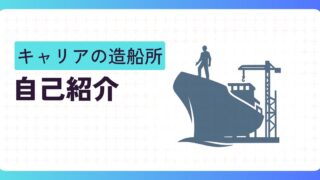
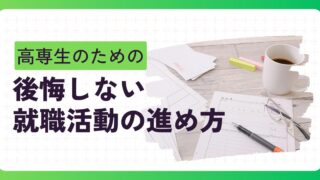
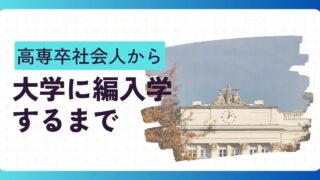
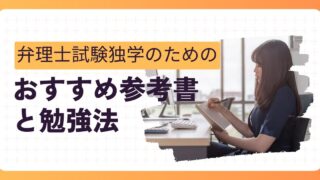
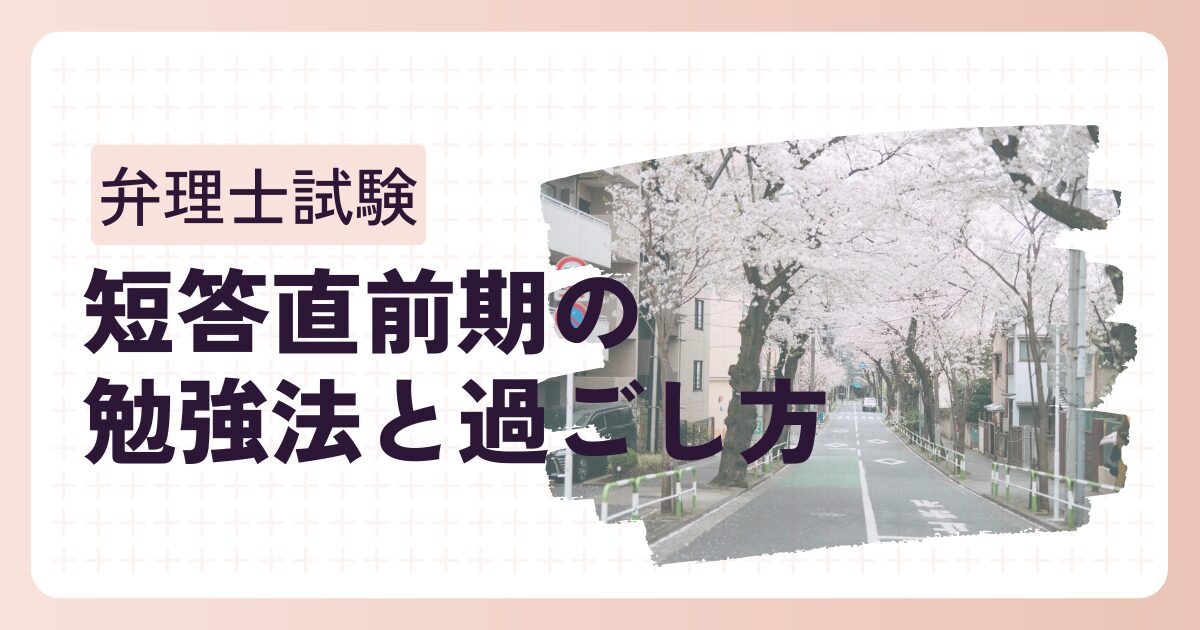
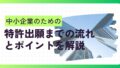
コメント