知財についてあまり注目される機会は少ないですが、知財を知らずにビジネスと進めると思わぬ形でビジネスが止まったり損害を被るリスクがあります。
一方で、知財を上手く活用することでビジネスを有利に進めることも可能になります。
知財部がない中小企業やベンチャー企業が知財について知り、活用するきっかけになればと思い、知財を知らないことによるリスクと知財の活用について造船所を舞台にした仮想事例を交えて解説します。
仮想事例
熊野造船は広島県の熊野町にある主に小型貨物船を建造する造船所です。造船業界の中では小規模な造船所です。

熊野造船は造船業界の中では小規模な造船所ですが、省エネ技術に強みを持っています。
熊野造船は研究の末に船の船尾部分に特殊な形状をしたフィン(イラストの黄色いひれ状箇所)をつけることで船の燃費を向上させる技術を開発しました。

熊野造船は船にフィンを取り付けて顧客の船会社に引き渡し、さらに、フィンに「Xフィン」という名前をつけてカタログにも写真付きで掲載してアピールを始めました。
権利として保護しておかないと真似されても何も言えない
宇佐重工業は大分県の宇佐市にある熊野造船よりも遥かに大きな生産能力を有する大手重工メーカーです。

宇佐重工業は就航している熊野造船で建造された船についているXフィンを見て、自社の船にもXフィンを模倣したフィンを取り付けて建造して引き渡しを始めました。
その結果、コスト競争力で劣る熊野造船の受注量は減少してしまいました。熊野造船は宇佐重工業が自社のXフィンを模倣していると思い、宇佐重工業に問い合わせてみました。

貴社の船についているフィンは弊社が先に開発したXフィンを模倣したものと思われるのでフィンの取り付けを止めていただきたい。

弊社は御社の建造船やカタログで公知になっている公知技術を権利が存在しないことを確認した上で実施しているので問題ないと考えています。

・・・。
熊野造船側は何も権利を持っていないので宇佐重工業に全く取り合ってもらえず、これ以上何も言うこともできませんでした。
まとめ
「Xフィン」は熊野造船にとって、差別化技術かつ船の外観から形状を容易に把握することができるものなので、「Xフィン」について特許出願して権利化して保護しておくべきでした。
特許権を取得する理由について代表的なもの簡単にまとめます。
- 発明の独占権を得るため
- 他者が同じ技術を無断で製造・販売・使用するのを差し止めたり損害賠償請求する。
- 競合他社へのけん制
- 競合他社による模倣や市場への新規参入を抑制する。
- ライセンス収入を得るため
- 他社に特許を使わせて使用料(ロイヤリティ)を得る。
- 企業価値・技術力のアピール
- 投資家・顧客・取引先への信頼性向上や、広報・営業ツールとしての活用。
発明を公開するまえに特許出願を済ませておく
時間を巻き戻して、熊野造船の熊野社長は、他社に模倣されないように「Xフィン」について特許を取得することにしました。そこで、特許事務所の弁理士に相談に行きました。そして、「Xフィン」の技術内容やビジネスについて一通り説明しました。

「Xフィン」は弊社の差別化技術で、特許出願したいのでアドバイスをお願いします。

「Xフィン」は特許出願しておいた方がよさそうですね。先ず、「Xフィン」についてホームページに掲載したり船を引き渡す前に特許出願を済ませておく必要があります。そのため、「Xフィン」を公開する予定を教えてください。
まとめ
新技術を開発した場合、この技術が特許として権利化すべき技術なのかを検討して、公開する前に出願を済ませておく必要があります。
特許出願前に公に公開されている発明について特許出願しても新規性がないとして特許にならないためです。
出願しようとしている発明に新規性があるのか調査する方法については、下記にまとめています。
初心者向け 特許調査のやり方
特許出願しない方がいい場合もある
熊野造船では、「Xフィン」以外にもエンジンの制御プログラムを工夫して燃費を向上させる技術を開発しました。熊野社長はエンジンの制御プログラムについても弁理士に相談してみました。

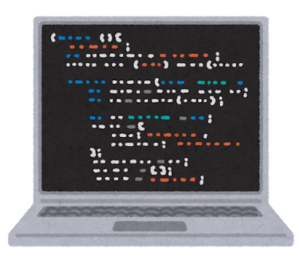

このエンジンの制御プログラムのロジックも特許で保護したいのですがいかがでしょうか?

特許出願をするとその内容が出願から1年半後に公開されます。公開されることで他社に技術開発のヒントを与えることになります。ちなみに、競合他社がこの制御ロジックを実装していることを調べることは可能ですか?

他社の船に乗り込んでエンジンのコントローラを解析するのは無理ですね...。
まとめ
特許出願すると、出願から1年半後にその内容が公開公報として公開されます(出願公開という)。
今回のエンジンの制御プログラムのように侵害の立証が困難ものを出願すると、技術を公開したにも関わらず権利行使ができないといった事態にもなり得ます。
ただし、カタログや商談でアピールするような内容であれば、侵害立証が難しくても特許出願した方がいいケースもあります。
意匠登録出願も検討してみる

今回の「Xフィン」を権利化する場合、フィンの長さや幅、厚みを文章で表現して権利内容(特許請求の範囲)を記載する必要があります。それだと、パラメータを少し変更するだけで他社に回避されるリスクがあるので意匠登録出願も検討されてはいかがでしょうか?
まとめ
特許の場合、権利にしたい内容を文章として「特許請求の範囲」に記載して出願・権利化をします。したがって、「特許請求の範囲」の記載の仕方によって権利範囲が変動したり、他社の模倣品を上手く権利範囲に含むことごできないといった事態が起こり得ます。
そこで、物のデザインを保護する「意匠権」という形での権利化も検討してみるとよいと思います。
意匠は図面によって意匠を特定して出願し、意匠権は図面に描かれた意匠とそれに類似する意匠にも及ぶため、特許ではカバーしきれない模倣品に対しても権利行使ができるようになります。
また、特許出願のように大量の文章(明細書等)が必要ないため、特許出願と比べて安価かつ早期に権利化することができます。

このように特性の異なる知的財産権を組み合わせて製品やビジネスを保護することを「知財ミックス戦略」と呼びます。
商標登録出願も検討してみる
熊野造船では開発したフィンに「Xフィン」という名前を付けてホームページやカタログに載せて、船会社の一部でも熊野造船といえば「Xフィン」と認知され始めていました。
ところが、宇佐重工業が「Xフィン」という商標権を取得し、それに基づいて熊野造船に「Xフィン」の使用を止めるように警告書を送ってきました。

「Xフィン」の名前は弊社が考えて宇佐重工業の出願よりも前にカタログに載せていたのに理不尽です!

商標は特許と異なり新規性という考え方がないので、自分が使用を開始した後になって他人が商標登録してしまう場合があります。「Xフィン」が熊野造船のフィンであることは一部の船会社にしか知られていないので、先に使っているという主張(先使用権)も難しそうです。
まとめ
商標権は商品名やロゴマークといった自社の製品やサービスの出所を表示する文字や図形などを保護するものです。

商標の審査は先願主義(先に出願した者が登録を受けられる)の下に行われるので、自社が商標Aの使用を開始した後に他社が同じ商標Aを出願しても一定の要件を満たせば登録されることがあります。救済制度もありますが、一定の要件を満たす必要があり、必ずしも救済されるわけではないので安心はできません。
自社が使用する商標については、他社に先を越されないように出願・登録しておくことをおすすめします。出願・登録にかかる費用もそこまで高くはなく、他人に登録されるリスクを解消できるのでコストパフォーマンスもよいかと思います。
全体のまとめ
以上、知財についての代表的なリスクとその予防策について解説しました。実際の事例はさらに複雑になるので、特許事務所や都道府県の発明協会など知財についての相談先を持っておくとよいと思います。
知財についてさらに詳しく知りたい方は下記の書籍を読んでみるとよいと思います。知財の専門家(弁理士、知財部員)ではない方(経営者、技術者など)向けに知財の全体像がわかりやすく解説されています。この2冊は、私が初めて購入して読んだ知財の書籍です。

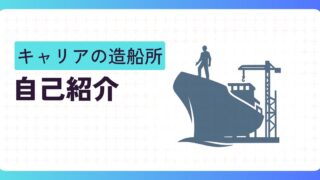
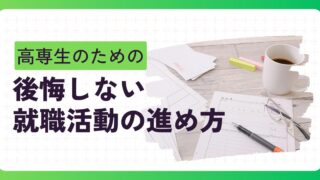
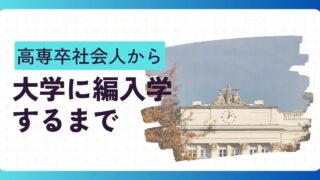
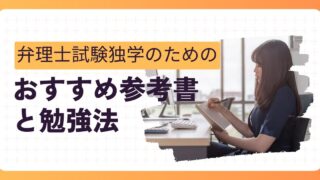
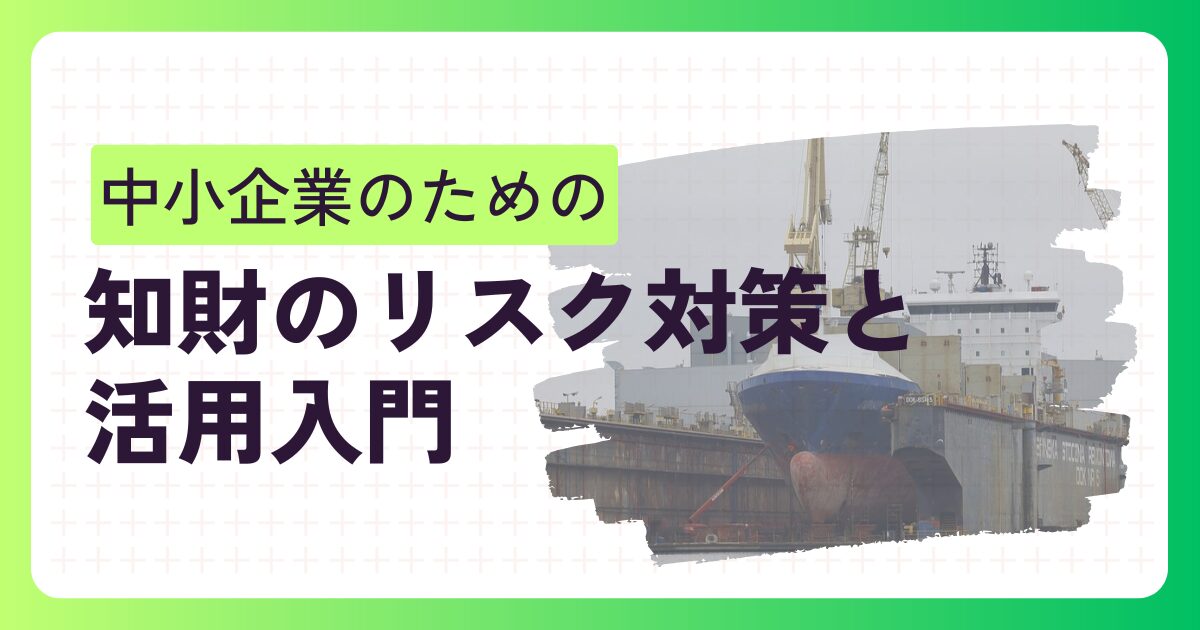

コメント