記事内に商品プロモーションを含む場合があります
費用などの都合で資格予備校に通わずにオンライン講座を視聴したり独学する場合、市販の参考書を活用することが必要になります。
しかし、どの参考書も分厚いものばかりでどう使って勉強すればよいのか、何を選ぶべきなのか見当がつかない人も多いと思います。
私はオンライン講座と市販の参考書を活用して最小限の費用(約15万円)で弁理士試験に合格できました。その経験をもとにおすすめの参考書・テキスト・教材とその使い方を紹介します。
弁理士試験に興味を持ったら読むべき本
弁理士資格に興味はあるけれど、「難しそうだけど勉強が続けられるか不安」、「資格予備校やオンライン講座はそれなりの価格で躊躇している」という方も多いと思います。

資格予備校やオンライン講座を受講し始めて「思っていたものと違う」、「興味が湧かなくて続けられそうにない」といったことにならないように、先ずは、弁理士試験全体について大まかに解説したテキストを読んでみるとよいと思います。
勉強のコツや試験のポイントについても解説されているので勉強法で迷ったときの羅針盤にもなると思います。このような書籍はいくつか出版されていますが、私は、下記の本で弁理士試験の全体像を掴みました。
また、私はオンライン講座の「スタディング」を受講したので「スタディング」の伊藤講師の書籍も紹介しておきます。
メインの教材としてオンライン講座を利用
お金をあまり掛けないことが本記事の趣旨ですが、弁理士試験を書店の本だけで突破するのは困難です。
それは、出題範囲が膨大である上に、個々の専門書は存在するものの試験用ではないので、初学者が読み進められるようなものではないためです。
そのため、何らかの形で最初から最後まで講師による「弁理士試験向けの授業」を受ける必要があります。
どの講座を選ぶかについては、どれでもよいと思いますが予算と自身の勉強のやり方と合っているかで決めるとよいと思います。
資格予備校とオンライン講座の比較については、下記の記事にまとめています。
弁理士試験のための資格予備校・講座の徹底比較
私は、費用を抑えたかったのと、「自分の勉強のやり方」がある程度確立していたのでオンライン講座を選びました。

オンライン講座はどれを選んでもよいのですが、私は、オンライン講座の中でも最も価格の安い「スタディング」で弁理士試験に合格しました。

予算に応じて「アガルート」や「資格スクエア」を選んでもよいと思います。価格によってサポートの手厚さが変わってきます。
サブの教材として必要な参考書・テキスト
短答試験に必要な参考書・テキスト
短答試験では、オンライン講座以外に法文集、過去問集、模試があれば十分です。
短答は条文理解が問われるのでそれ以外の参考書には手を出さず法文集と過去問を使いながら条文を徹底的に理解したいです。
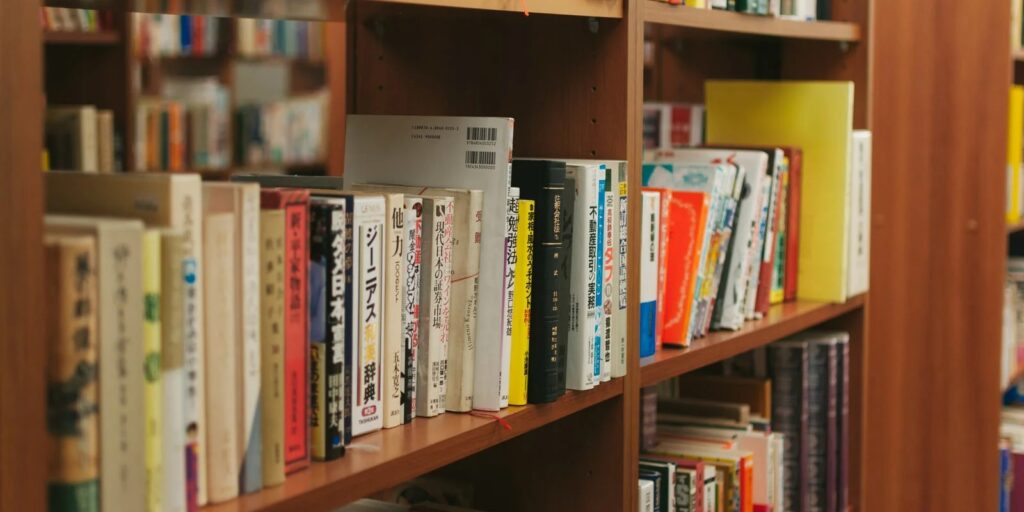
四法対照は必須
弁理士試験は法律の試験なので法文集は必須です。法文集は四法対照を使って特許、実用新案、意匠、商標を対比しながら書き込みやマーカーを引いて「自分だけの法文集」を作り上げていきます。
過去問集は必須
メインの教材(オンライン講座)を一周したら、過去問集を何度も回していきます。
過去問集の王道はLECの短答過去問集で、解説が丁寧かつ正確性が高いので学習効率も上がると思います。
工業所有権法逐条解説(青本)はなくても可
カバーが青いので青本と呼ばれている本です。条文の解説集といったところで、資格予備校のテキストもこの本が出典となっていることが多いです。
かなり分厚く重いので持ち運びも大変で、法改正があると最新版ではなくなってしまいます。
特許庁のホームページでpdfが無料で公開されているので、購入する必要性は低いです。ただし、わからないところを辞書的に調べる目的で購入してもよいかと思います。
私は購入したものの、少しマーカーを引いたくらいで短答式試験の学習ではあまり使わなかったです。優先度的には、講座のテキスト→過去問→法文集→青本といった順番です。
短答模試
資格予備校が行っている模試に参加して、本番に近い環境に慣れておきたいところです。
短答式試験はマークシートなので費用はそこまで高くはないです。資格予備校が近くにない人は自宅受験になりますがそれでも参加しておきましょう。模試はLECやTACが王道です。
短答式試験のまとめ
弁理士試験の短答式試験の教材は下記の通りです。どの試験にも共通することですが過去問と王道の教材で学習して、様々な教材に中途半端に手を出さないことが大事だと思います。
- 講座(資格予備校またはオンライン講座)
- 四法対照
- 短答過去問集
- 短答模試
最後に、やや精神論的な内容ですが、短答試験では、たかが1点で笑う人と泣く人が多くいます。私も39点ギリギリでの合格でした。そのため、1点を全力で取りにいくつもりで試験当日まで勉強をやり抜く姿勢が大事だと思います。

論文試験に必要な参考書・テキスト
論文式試験は、特許・実用新案、意匠、商標の3科目に分かれています。それぞれの科目の概要と試験の流れは下記の通りです。
また、試験中に貸与法文を自由に見ることができます。
- 午前
- 特許・実用新案は問題1と問題2に分かれていて、それぞれ、A3用紙2枚の答案用紙が与えられて解答時間は2時間です。問題1と問題2は複数の小問題から構成されています。
- 昼休憩
- 午後
- 意匠、は問題1のみで、A3用紙2枚の答案用紙が与えられて解答時間は1時間30分です。問題1は複数の小問題から構成されています。
- 商標、は問題1のみで、A3用紙2枚の答案用紙が与えられて解答時間は1時間30分です。問題1は複数の小問題から構成されています。
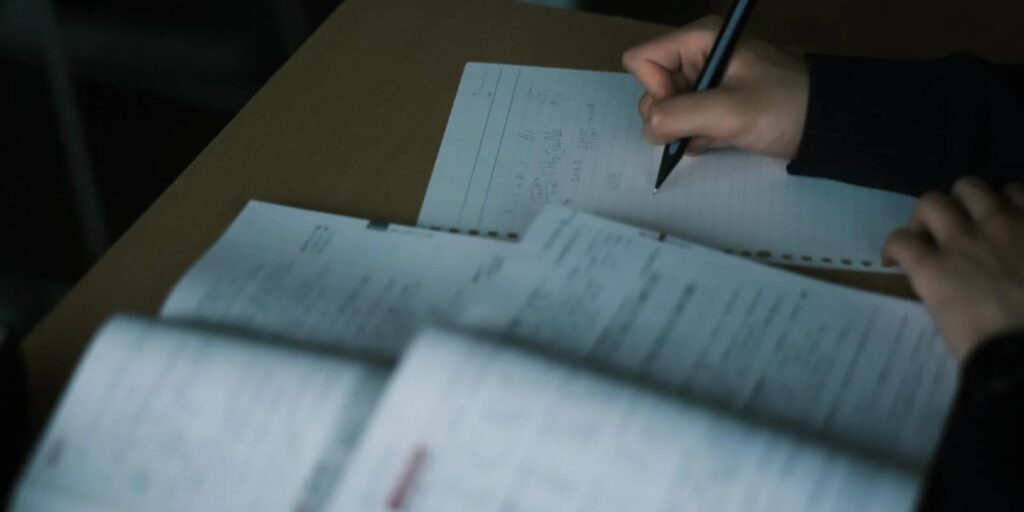
このことからわかるように、特許・実用新案は問題1と問題2があるにも関わらず解答時間が2時間しかありません。
商標、意匠は1問題あたり1時間30分使えますが特許・実用新案は1問題あたり1時間しか使えないので時間管理が非常にシビアです。
さらに、特許・実用新案の問題1は合否を決める選択を迫られるような問題がよく出されるので、試験開始の緊張や時間の少なさからくるパニック状態を乗り越えて正確な結論を出すことが求められます。
特許・実用新案が不出来で心が折れると午後の意匠、商標にも響いてきます。そのため、特許・実用新案が特に重要かつ難しいです。
論文の作法や暗記事項を確認
論文式試験の勉強を始めるにあたっては、先ず基本的な論文の書き方を資格予備校のテキストや参考書で確認します。
細かなところはテキストで解説されているので省略しますが、下記の法的三段論法は極めて重要かつ常に意識して書くようにしたいです。
- 規範定立
- 当てはめ
- 結論
市販のテキストなら私も使った下記がおすすめです。このテキストは暗記事項集としても活用しましょう。
他に重要だと思う作法としては、「聞かれていることに端的に答える(余計なことは書かない)」ことだと思います。
余計なことを書いても意味がないか、減点されるか、その記載に時間をとられて他の記載が疎かになるだけで百害あって一利なしです。
分量としては1問題あたりA3用紙1.5枚分書けば十分です。私はそれで合格できました。
過去問集の使い方
先ずは過去問の模範答案を写経
いきなり過去問を解こうとしても白紙の答案用紙を前に途方に暮れるかと思います。
なので、先ずはハードルを下げて模範答案を写経します。過去10年分程写経すれば論文式試験の解答イメージや出題傾向が掴めると思います。
写経ばかりしていても自分で書けるようにはならないので程々にして次のステップに進みます。
過去問を小分けにして自分で書いてみる
いきなり、全文書き(本番同様にA3用紙2枚分書く)はハードルが高いので過去問の大問題を小問題に小分けにして時間を計りながら書いてみます。
小問題を1問書いたらすぐに模範答案を読んで自分の答案との違いを確認して次に活かします。
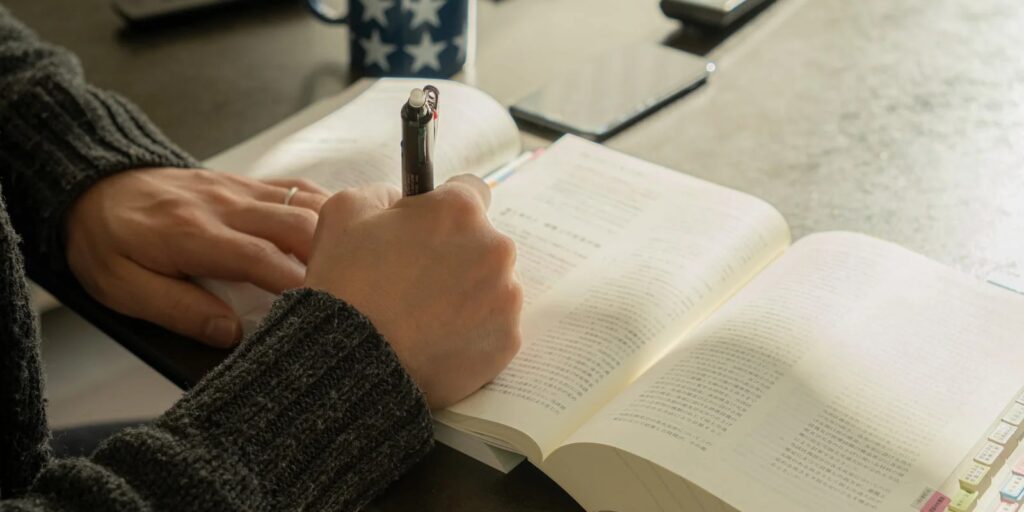
実際に手を動かすスポーツのようなものなのでやればやるだけ解答(手書き)スピードも速くなります。
ここで、使う法文集は四法対照ではなく、試験時に貸与される法文集に近い構成のものを使いましょう。合格者の知り合いやフリマサイト、オークションサイトで本物の法文集を入手するのがベストです。
このステップでは、過去問の内容は時間内に当たり前に書けるという状態まで持っていきます。ボールペンを何本も空にして答案用紙が山のように積みあがるつらい道のりですが頑張るしかありません。
また、たまには全文書きをして本番に近い状況にも慣れておきましょう。
論文答練(中古で可)を使って様々な問題に触れる
過去問をマスターするだけでは、合格できないのが弁理士試験の難しさです。過去問を一通り解けるようになったら資格予備校の答練を受講したいところですが、マークシートの短答答練と異なり人力で採点、添削するので、資格予備校の答練は10万円を軽く超えるかなり高価なものです。
私はお金がなかったので資格予備校の答練(採点、添削)は受けていません。

そこで、私はフリマサイトで資格予備校の答練の中古品を入手しました。
当然、採点や添削を受けることはできませんが、安いので様々な問題を多く入手することができます。
過去問を解くときと同様に、自分で解いて模範解答を確認するということを繰り返します。こうして量をこなすことで様々な問題に触れて、大抵の問題はカバーできる力を鍛えていきます。
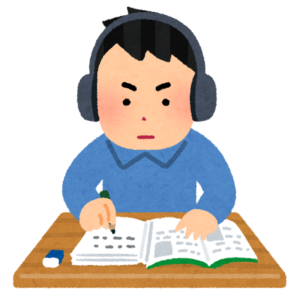
LEC口述アドヴァンスドテキスト
口述試験用のテキストですが、口述試験で問われることは論文式試験で問われる可能性が高いです。
小問題で「~趣旨を説明せよ」といった一行問題に対応できる力が鍛えられます。
LECのサイトで購入できるので購入しておきましょう。これを早めにやっておけば、口述試験対策もかなり楽になります。
知的財産法判例教室
論文式試験では判例の知識が問われることがあります。判例についてはこのテキストの内容を覚えただけですが十分かと思います。
他の受験生が書けない(落としても致命傷にはならない)ことを覚えるよりも他の受験生が当たり前に書いてくることをしっかり覚えましょう。
無料でできる情報収集テクニック
資格予備校の短答解答速報会
短答試験当日の夜に資格予備校による解答速報会があると思いますが、そこで、講師が短答試験の傾向から論文でどこが出そうか出題予想を話してくれると思うので聞き漏らさないようにしましょう。

講師は自分のクラスにも同じことを話しているはずなので、大多数の受験生は対策をしてきます。他の人が当たり前に解けることを落とすのは致命傷なのでしっかり対策をしましょう。
X(旧Twitter)
Xには多くの弁理士試験受験生がいてどんな勉強をしているのか情報発信しています。情報発信している受験生は優秀な人が多いです。彼らの投稿を基に他の受験生がどんな勉強をしているのか知ることも大事です。

論文式試験のまとめ
私が論文式試験に合格するためにしたことは以上の通りです。これだけですが十分に合格基準点を超えることができました。
振り返ると、知識が必要以上に増えると余計なことを書きがちになるのでこれぐらいの知識量が最も合格しやすいのかと思います
口述試験に必要な参考書・テキスト
論文合格発表から口述試験まで1カ月くらいしかありません。論文式試験に合格した優秀な受験生の1割は落ちるのですから、残された期間全力で勉強しましょう。合格はもうすぐです!

LEC口述アドヴァンスドテキスト
このテキストは丸暗記するくらいの勢いで徹底的にやり込みます。とにかく自分の口で声を出して回答する訓練を積みます。
家族や友人に協力してもらって問題を出してもらい、口頭で回答することを繰り返しながら自分の口で回答することに慣れておきましょう。

資格予備校の口述模試とその後にもらえるテキスト
論文に合格したら枠が埋まる前に速攻で申し込みます。大手予備校のLECとTAC両方押さえておきましょう。地方であっても交通費を惜しんではいけません。

そして、口述模試を受けると暗記事項をまとめたテキストがもらえます。このテキストは情報の宝庫ですので徹底的にやり込みます。
弁理士の会派の練習会
こちらも論文に合格したら枠が埋まる前に速攻で申し込みます。弁理士の先輩方が模擬試験をしてくれるのでできるだけ申し込んでおきます。とにかく場数を踏んで本番に慣れておきましょう。
工業所有権法逐条解説(青本)の読み込み
前述のテキストよりも優先度は低いですが青本も読み込んで、様々な質問に対応できるよう引き出しを増やしておきましょう。
まとめ
オンライン講座や独学の場合に用意すべき参考書・テキストについてまとめました。
いろんなテキストに中途半端に手を出さずに、これらをしっかりマスターすれば十分に合格できると思います。
細かな勉強テクニックは下記の記事にまとめていますので参考にしてみてください。
社会人が大学や難関資格に働きながら合格するための勉強法

皆様の合格をお祈りしています。

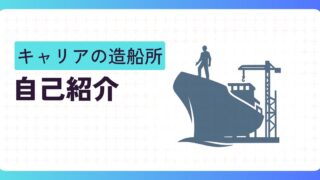
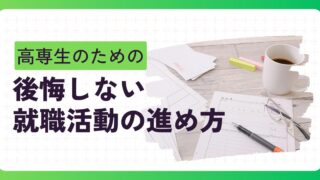
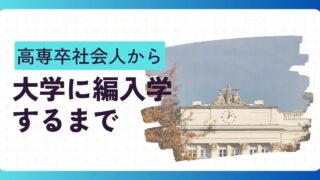
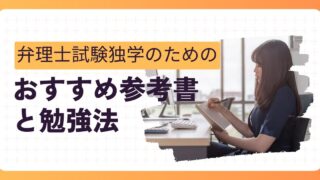
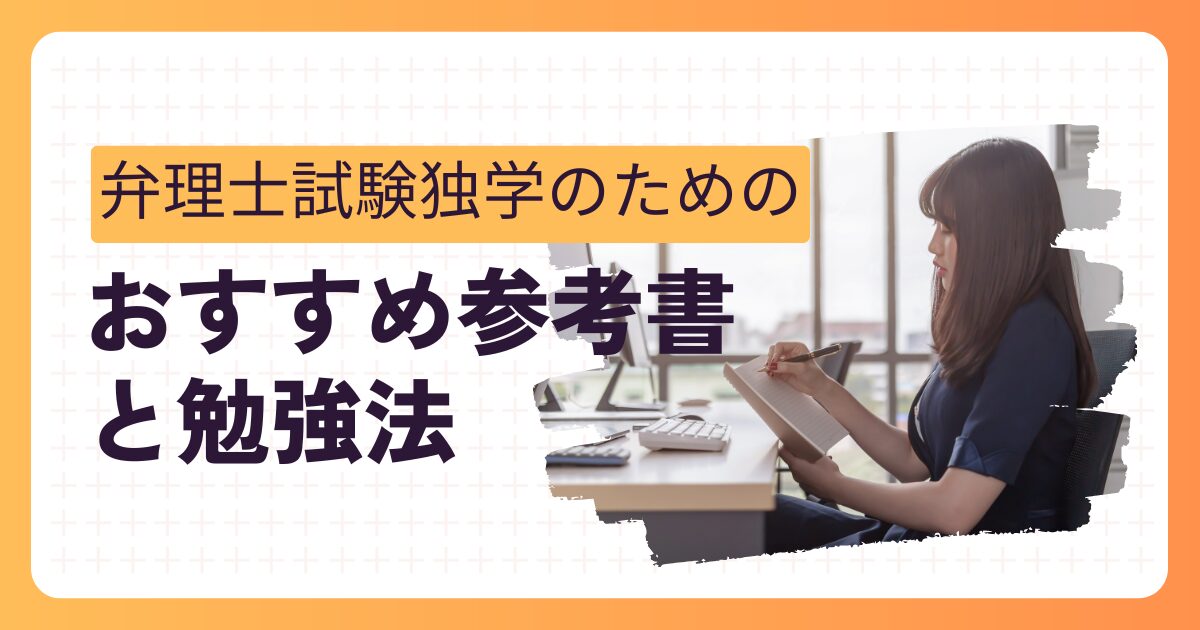
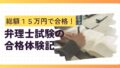
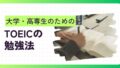
コメント